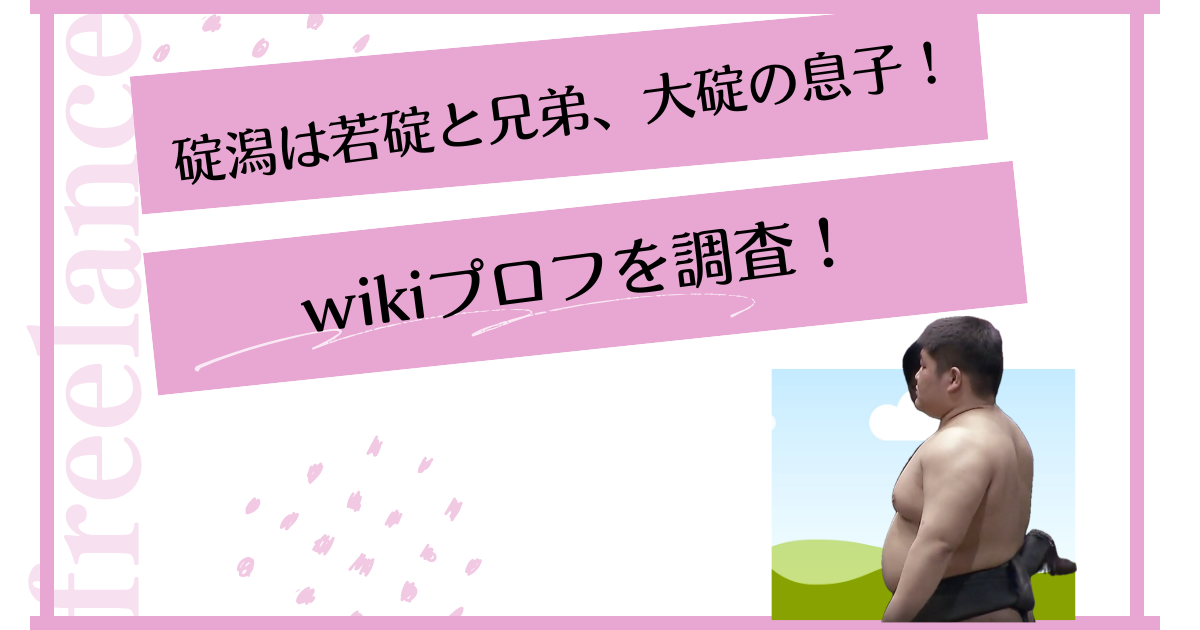碇潟という力士が話題になっています。その注目の理由のひとつは、彼の家族構成にあります。
碇潟は、同じ相撲界で活躍する若碇の兄弟であり、元力士・大碇の息子という相撲一家の出身。相撲界に生まれながら、どのようにして自らの足で土俵に立つ決意をしたのか、彼の背景には多くの興味深いストーリーが潜んでいます。ぜひ最後まで見て下さいね!

令和の兄弟横綱になるか!?要注目の力士です!
碇潟のwikiプロフィール


しこ名: 碇潟 忠剛(いかりがた ちゅうごう)
本名: 齋藤 忠剛(さいとう ちゅうごう)
生年月日: 2007年2月24日
年齢: 17歳
身長: 174.0cm
体重: 124.0kg
出身地: 京都府京都市西京区
学歴: 春江中学校→埼玉栄高等学校
所属部屋: 伊勢ノ海部屋
初土俵: 2024年1月場所
最高位: 三段目最下位格付出
得意技: 押し
碇潟の名前の由来は?
この名前は、碇潟の父である甲山親方(元幕内大碇)や兄の十両若碇と同じ文字が含まれており、家族の絆を象徴しています。碇潟自身も「いいしこ名をいただいた」と語り、父と兄の番付を超えたいという強い意志を持っています。
過去に「碇潟」という四股名で活躍した力士がおり、その名前を受け継いだ可能性があります。碇潟夘三郎(いかりがた うさぶろう)という力士が明治時代に活躍しました。彼の四股名が由来となっている場合も考えられますね。
- 明治時代に活躍した大相撲の力士
- 本名は不明
- 最高位は前頭
- 厳つい容貌で駆け引きが上手く、「雷獣」という異名を持つ
- 得意技は掻っ撥き(かっぱつ)
- 1908年5月場所で大関國見山を破る
- 1909年1月場所・6月場所で横綱太刀山を破る殊勲を挙げる
- 横綱常陸山の太刀持ちや露払いを務める
- 1914年5月場所に引退し、年寄名跡「山響(やまひびき)」を襲名
- 後に年寄名跡を「佐ノ山(さのやま)」に変更
- 広島での京阪合併相撲の帰りに常陸山に弟子入りを志願し、1901年に上京
- 1901年5月場所に三段目格で初土俵
- 1905年5月場所に十両昇進
- 1907年1月場所に新入幕
碇潟夘三郎(いかりがた うさぶろう)
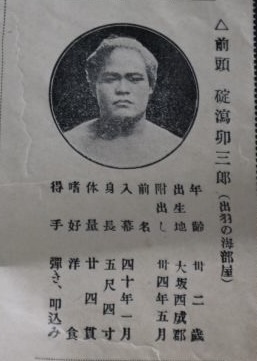
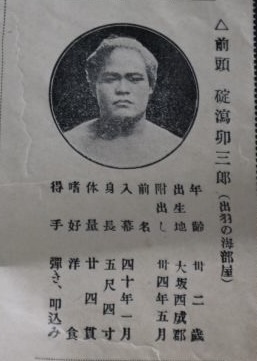
碇潟は若碇と兄弟?


十両・若碇(19=伊勢ノ海部屋)の弟の斎藤忠剛(17)は、父と兄と同じ伊勢ノ海部屋から受検
引用元:スポニチ 2024年12月27日
碇潟は若碇の弟です。若碇は十両に所属しており、碇潟は令和7年1月場所で新弟子としてデビューしたばかりの力士です。
若碇関については下記の記事をあわせてチェックして下さいね!🔽
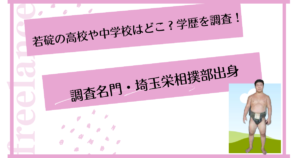
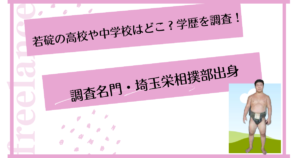
碇潟は大碇の息子?
大碇(甲山親方)
大碇関は、1995年3月場所で初土俵を踏み、1997年5月場所で新入幕を果たしました。最高位は前頭11枚目で、2004年11月に引退するまでの間に356勝336敗の成績を残しています。主に突き押しを得意とし、相撲界での活躍が評価されていました。
引退後、大碇関は甲山親方として伊勢ノ海部屋で後進の指導にあたっています。
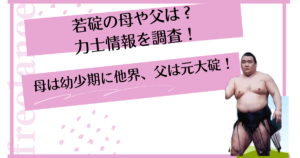
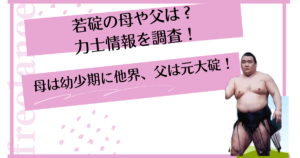
碇潟の学歴|出身中学校は?
春江中(江戸川区)


2007年(平19)2月24日生まれ、東京都江戸川区出身の17歳。台東区小松竜道場で幼少の頃から相撲を始め、江戸川区立春江中3年時に全国都道府県中学生大会8強
引用元:スポニチ 2024年12月27日
- 台東区小松竜道場で幼少の頃から相撲の稽古に励んでいた。
- 全国都道府県中学生大会8強(中学3年)
碇潟は、中学時代からその優れた相撲の才能を開花させました。全国都道府県中学生大会で堂々のベスト8入りを果たし、早くも「未来のスター」として注目を集める存在となったのです。この偉業は、彼の才能だけでなく、情熱と努力の結晶でもあります。その輝かしい成果は、相撲界での大きな可能性を秘めた若き力士として、彼の名を知らしめるきっかけとなりました。
そんな彼が力士としての基礎を築いたのが、台東区小松竜道場でした。この道場での稽古は決して易しいものではなく、技術や体力を鍛えるだけでなく、精神面の成長も求められる厳しい環境でした。指導者たちによる徹底した鍛錬を通じて、碇潟は基本をしっかりと身につけるとともに、勝負への覚悟や集中力も培いました。この道場での経験は、彼にとって何よりも貴重な糧となり、後のキャリアを切り拓く強固な基盤を築きました。



父・甲山親方(大碇)の遺伝子を受け継いだ磯。相撲に懸ける情熱、努力を惜しまない姿勢、そして道場での厳しい稽古から得た成長。それらが碇潟を今日の「期待の星」たらしめています。
碇潟の学歴|出身高校は?
埼玉栄高校
甲山親方(元幕内・大碇)の次男で十両・若碇(19=伊勢ノ海部屋)の弟の斎藤忠剛(17)は、父と兄と同じ伊勢ノ海部屋から受検。埼玉栄高3年で国民スポーツ大会少年の部ベスト4などの実績を持つ実力者。
- 高校1年生時:
全国高校選抜大会で3位入賞。
- 高校2年生時:
全日本体重別選手権ジュニア男子重量級(100kg以上)で3位入賞。
世界ジュニア選手権団体戦で優勝(先鋒として出場)。
国民体育大会(国体)で3位入賞。
- 高校3年生時:
関東大会無差別級で優勝。
全国高校総体でベスト8。
国民体育大会(国スポ)で4位入賞。
これらの成績は、彼が相撲界での地位を築く大きな足掛かりとなりました。埼玉栄高校の相撲部で培った経験は、全国レベルでの競争を通じて彼の実力をさらに引き上げました。この環境での厳しいトレーニングが、彼の技術や精神面の成長に寄与したことは間違いありません。
さらに、磯潟はこれらの経験を通じて相撲だけでなく自身の考え方にも変化があったと語っています。競技に臨む姿勢や日常生活での心構えを見直すことで、競技中のパフォーマンスに一層磨きがかかりました。



この精神的な強さが彼の特徴であり、将来のさらなる飛躍を期待させます。